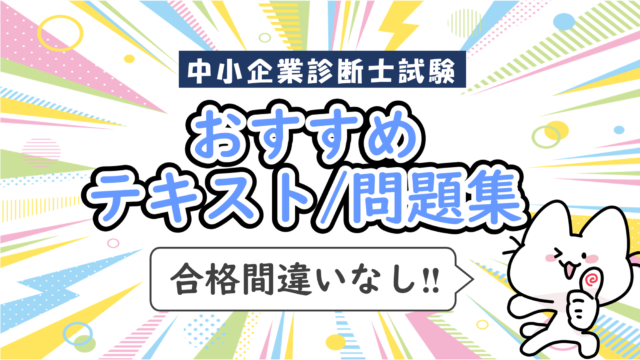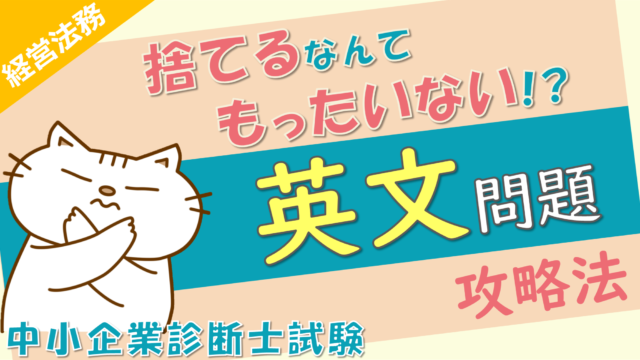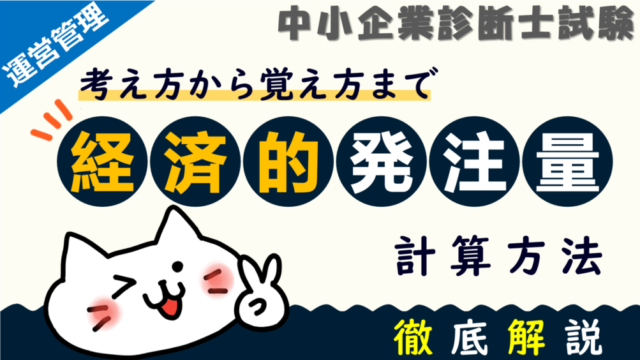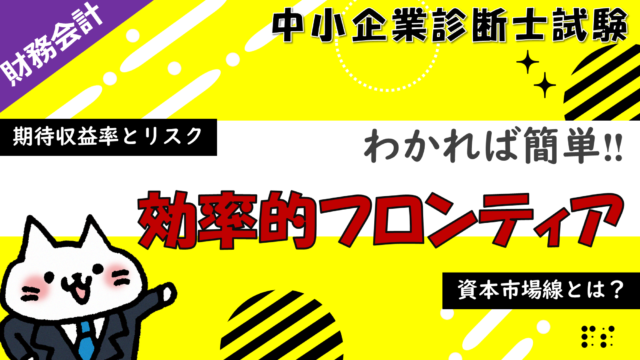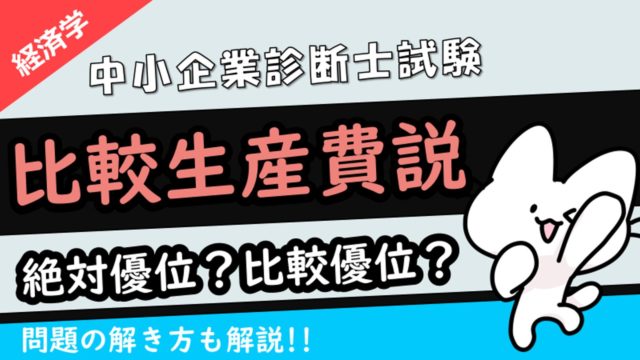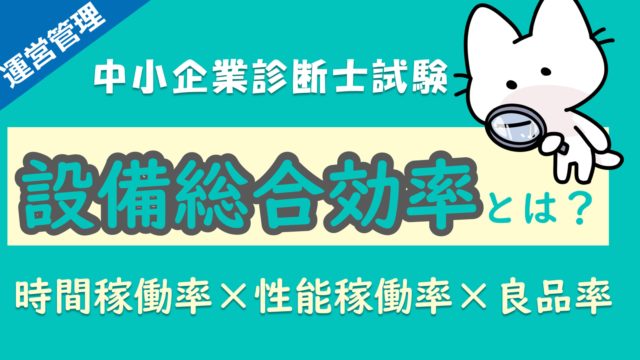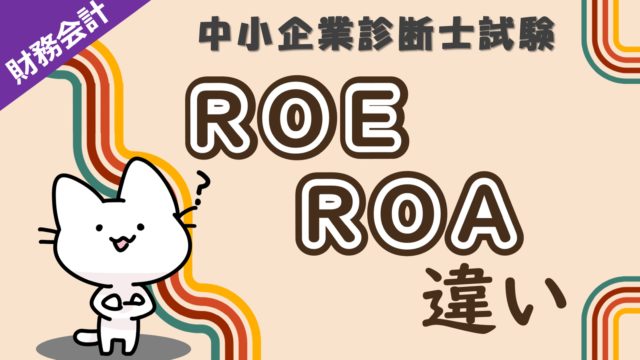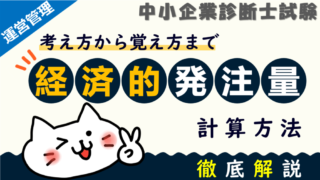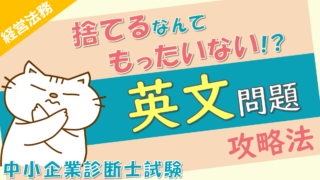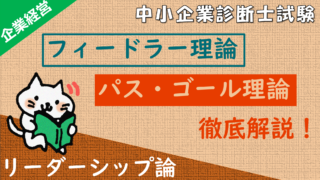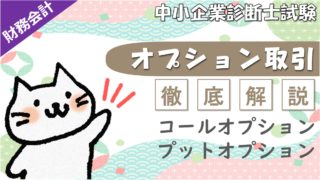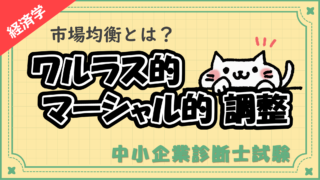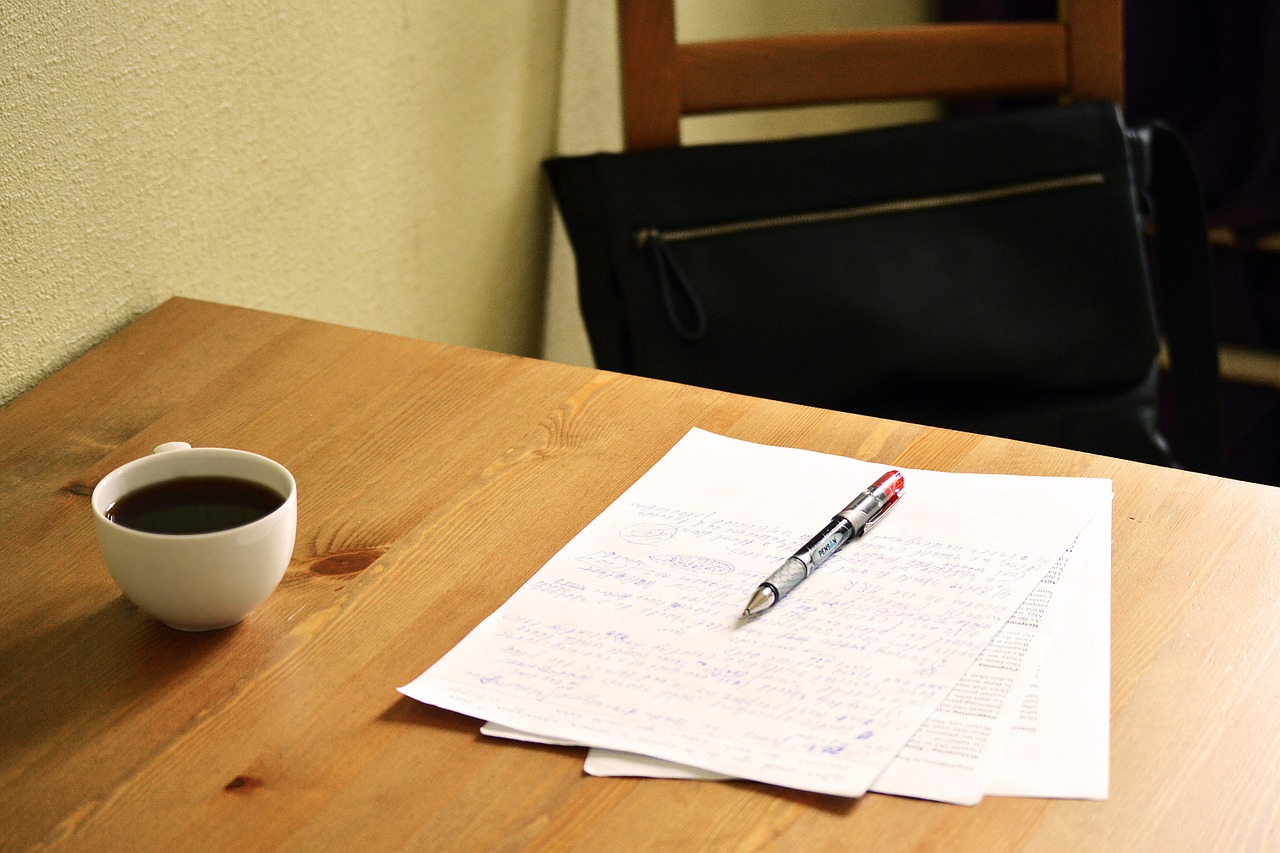はいどうも、中小企業診断士のたかぴーです。
今回は、一次試験合格に必要な得点パターンと解答テクニックというテーマで解説していきたいと思います。
GWが終わり、いよいよ直前期と呼ばれる期間に入りましたので、そろそろ本番を意識した学習をしていきたいところです。
この記事を見れば、どのような得点パターンで合格点を獲得すればよいのか、そしてそのために必要な勉強方法やテクニックが分かるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
合格に必要な得点パターンとは?
まずは合格に必要な得点パターンです。
皆さんご存じの通り、診断士試験では1科目あたり60点が必要となりますが、合格者は確実にわかる問題だけで60点を得点しているわけではありません。
例えば60分科目ですと、全25問が1問4点で出題されますが、自信を持って回答した問題が15問あって、勉強不足でわからなかった問題が残りの10問ある、というわけではないということです。
多くの方が勘違いしていますが、これは間違った認識です。
とにかく25問のうち、自分が自信を持って答えられる問題を15問探して得点する、という認識で試験に臨むと、想像以上に本試験が難しく感じてしまうでしょう。
では、本試験ではどのようにして60点を積み上げていくべきか、順を追って説明していきたいと思います。
自信を持って正解できる問題とは?
ここから、いくつかの問題のタイプをご紹介したいと思います。
まずは、自信を持って正解できる問題ですね。
こちらには、次の3パターンがあります。
まず一つ目が、全選択肢がわかる問題です。
正解選択肢に自信が持てるし、間違い選択肢のどこが間違っているのかも、自信を持って指摘できるような問題です。
例えば、選択肢が4つあって、選択肢アが正解だったときに、全選択肢の内容がわかっているので、自信を持って答えられるイメージですね。
このタイプの問題が多ければ楽なのですが、本試験ではほとんど見かけないタイプの問題です。
2つ目が、正解だけはわかるような問題です。
正解選択肢だけは自信を持って正解と答えられるのですが、間違い選択肢については、どこが間違っているのか、よくわからないような問題です。
例えば、正解選択肢のアだけは、合っていることがわかるけど、他の選択肢には初めて見た単語が並んでいようなイメージですね。
間違い選択肢のうち、1個~2個は間違いを説明できるというケースもこちらに含まれます。
自信を持って答えられる問題のほとんどは、このタイプになるかと思います。
3つ目が、正解だけがわからない問題です。
正解選択肢だけ自信がなく、その他の間違い選択肢は確実に間違っていると自信を持って答えられる問題ですね。
例えば、正解選択肢のアだけは、初めて見る単語の説明がされていて、他の選択肢は、明らかに間違ったに内容の説明がされているイメージですね。
この場合は、消去法的に正解を選んでいくことになります。
以上のような問題が、正答率60%以上の、いわゆるABランク問題になっているとお考え下さい。
しっかりと勉強した人であれば、確実に正答しておきたい問題ですね。
ですが、このような問題は、本試験では10問程度、約40点分しか出題されません。
自信を持って回答できる問題だけで、足切り回避分の得点しか獲得できないイメージですね。
確率で正解できる問題とは?
続いて、確率で正解できる問題です。
これは、自信を持って正解を選べるわけではないが、ある程度の確率で正解できる問題を指します。
例えば、2択にまで絞れる問題ですね。
先ほどまでのように、正解選択肢がわかるわけではないけど、間違い選択肢のうち、2つを自信を持って削れるような問題です。
例えば、間違い選択肢のウとエは確実に間違いだとわかっていて、アかウのどちらかが、正解だと絞れるようなイメージです。
この場合、理論的には50%の確率で正解を選べることになりますね。
また、同じように3択まで絞れるよう問題もあります。
この場合は、間違い選択肢を1つだけ潰せるというわけですね。
例えば、選択肢エだけは絶対に間違いだけど、他3つが悩ましいといったイメージですね。
この場合であっても、理論的には1/3、つまり33%の確率で正解できる計算です。
こういった問題が、正答率40%~60%の、いわゆるCランクの問題だと言えます。
正答率50%と言われると、全受験生のうち半分は正解選択肢を自信をもって選べた、という印象を受けますが、多くの受験生が2択まで絞って、半分は正解できたと捉えた方が、実態に近いと思います。
過去問でCランクの問題を復習する際は、少なくとも2択にまで絞れたか、という観点で振り返ってみても良いかもしれません。
本試験では、全25問のうち10問程度がこのタイプの問題となりますので、全て2択にまで絞れたとしたら、確率で20点分は獲得できる計算となります。
100%自信を持って答えている問題でなくても、そこそこの点数が積み上がるわけですね。
全くわからない問題
忘れてはならないのが、全くわからない問題です。
どの選択肢も意味が分からず、全く自身が持てないような問題というイメージです。
例えば、たかぴーの出身地を聞かれて、この中から正解選択肢を選べる人がいるでしょうか?
ア 宮城県
イ 秋田県
ウ 福島県
エ 山形県
僕と個人的な知り合いでない限り、さすがに当てずっぽうで答えるしかないはずです。
このような、そんなの知らないよという問題が、正答率40%未満の、いわゆるDEランクの問題だと言えます。
本試験では、5問程度が出題され、1/4の確率で正解できたなら、確率で4点取れるイメージですね。
作問者が100点を取らせないため、そして受験生を精神的に揺さぶるために、このような問題が出されるのだと思います。
このタイプの問題は悩んでも仕方がないので、さっさと適当にマークして、他の問題に時間を割きたいところです。
合格に必要な得点パターン
それでは、ここまでの内容を一度振り返ってみましょう。
本試験の問題は、自信を持って正解できる問題、確率で正解できる問題、全く分からない問題の3つに分類できるのでしたね。

自信を持って正解できる問題は確実に正解して40点をキープし、確率で正解できる問題はできるだけ2択にまで絞り込んで、20点分を積み上げ、全くわからない問題は、4点分獲得できればラッキーと捉えます。
そして、これらの合計で64点くらいを目指していくというのが、合格者の得点パターンとして、実態に近いと思います。
もちろん、それぞれの出題数はあくまで目安ですので、その点はご了承ください。
このことを前提に考えると、より確実に合格に近づくためには、3択を2択に、2択を1択に絞る力を身に付ける必要があることがわかります。
ここからは、そのためにどうすればよいか、ということを説明したいと思います。
得点向上に必要な勉強 (知識編)
まずは、勉強内容に触れていきたいと思います。
得点力向上に必要なのは、徹底的な過去問対策です。
当たり前かと思われるかもしれませんが、これを疎かにして涙を飲む方が、毎年あまりにも多いので何度でも言います。
過去問対策は、何よりも重要です。
これは作問者の気持ちになればわかるのですが、国家資格である以上、作問者は合格者0人なんて自体は避けたいはずですし、ちゃんと勉強した人は合格させたいはずです。

そうなると、作問者は徹底した過去問研究をするはずです。
過去問研究では、どんな問題を出題すると、どれくらいの正答率があるかが過去のデータからわかるはずです。
その上で、過去の出題内容を少しだけひねった問題と、新論点を散りばめて出題すれば、合格率の予測もしやすなります。
ですので、我々受験生サイドからすると、過去問に掲載の各種論点が十分に理解できれば、合格点は取れる内容をになっていると考えるのが合理的かと思います。
過去問がどのように出題されるか?
それでは実際に、過去問がどのような形で出題さるかを確認してみましょう。
例えば以下は、僕が実際に受験した令和3年度の経営法務の問題です。
選択肢アでは、アイスクリームは時間が経つと形が変わるから、意匠登録できないとしています。
意匠登録制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア アイスクリームの形状は時間の経過により変化するため、意匠登録できる場合はない。
エ 同時に使用される一組の飲食用ナイフ、フォーク、スプーンのセットの各々に同一の模様を施したとしても、これらを一意匠として出願し登録することはできない。
ここで、平成28年度 第8問の選択肢イを見てみましょう。
イ X 氏 :弊社のアイスクリームのヒット商品「診断くん」のデザインを一新しました。ぜひとも意匠登録をして模倣品対策をしたいのですが、意匠登録は可能でしょうか。
あなた:はい、意匠登録は可能です。アイスクリームは、時間の経過によりその形態が変化してしまいます。しかし取引時には固定した形態を有しているので、意匠登録の対象となることはあります。
令和3年度と同じようにアイスクリームの形状変化と意匠登録について聞かれており、アイスの形状変化しても意匠登録できるとしている、選択肢イが正解でした。
反対に、令和3年度は、意匠登録できないとしているので、誤りとなりますね。
続いて、令和3年度の選択肢エでは、ナイフ・フォーク・スプーンのセットで意匠登録できないとしています。
こちも平成25年度 第10問の選択肢アを見てみましょう。
ア Aは組物の意匠として一組の飲食用ナイフ、スプーン及びフォークのセットの意匠登録を受けた。Aの当該意匠権の効力は、ナイフのみの意匠には及ばない。
ナイフ・スプーン・フォークのセットで意匠登録を受けたと記載されていて、この問題では、この選択肢アが正解でした。
ですので、令和3年度は、意匠登録できないとしているので、誤りとわかります。
以上のように、わざわざ「アイスクリーム」「ナイフ・フォーム・スプーンのセット」という単語まで合わせて出題してくれています。
「過去問にある問題だから、勉強した人は確実に得点してほしい」という、作問者からの強いメッセージを感じる問題ですね。
このように過去問対策することで、正解選択肢を絞り込むことができることが、お分かりいただけたかと思います。
日々の過去問演習では、正解選択肢を選べるだけでなく、間違い選択肢のどこが間違いなのか、どのように記述を修正すれば正解となるのか、といった観点で徹底的に勉強することを意識してみてください。
得点力向上に必要な選択肢の絞り方 (テクニック編)
今度はテクニック編ということで、選択肢の絞り方を紹介したいと思います。
試験慣れている方からすれば、当たり前の内容ではありますが、これを知っているかどうかで、得点が変わってくるかと思います。
読点で区切って正誤判定する
まずは、「読点で区切って正誤判定する」です。
例えば、選択肢に以下のような記述があったときに、読点にスラッシュ(/)を入れて、一つ一つの内容を吟味するようなイメージですね。
例:事業ドメインの決定は、/将来手掛ける事業をどう定義するかの決定であり、/日常のオペレーションに直接関連し、/全社戦略策定の第一歩として競争戦略に結び付ける役割を果たす。
この選択肢の場合、事業ドメインは、日常のオペレーションに直接関連するという部分は合っていますが、全社戦略策定のために行われるわけでないので誤り、と判断します。
極端に強調した表現は疑う
続いて2つ目は、「極端に強調した表現は疑う」です。
願書には、明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書をすべて必ず添付しなければならない。
例えば選択肢に、「すべて」「必ず」「いかなる場合でも」といった限定するような言い回しが入っているケースですね。
世の中には絶対と言い切れることの方が少ないので、このような表現があるだけで、間違い選択肢である可能性が高くなります。
説明の入れ替え選択肢を削る
3つ目は、「説明の入れ替え選択肢を削る」です。
例えば、以下のような2つの選択肢があったときに、選択肢アは、内容が製番管理方式となっています。
ア 追番管理方式では、製番番号が異なれば同じ部品であっても違った部品として管理される。
イ 製番管理方式では、受注見積もり時点で信頼できる納期を提示できる。
この時点で、選択肢イは製番管理方式の内容説明になっていますが、恐らく間違っているだろうと疑った方が良いです。
もちろん、選択肢イが正解選択肢となる場合もありますが、迷ったときの心得としてご紹介しました。
反対表現・対照表現を削る
続いて、「反対表現・対照表現を削る」です。
例えば以下のような選択肢があったときに、対象のグラフが貨幣需要なのか、投資需要の内容なのかがわかるだけで、選択肢が半分に削れます。
ア 貨幣需要の利子弾力性がゼロである。
イ 貨幣需要の利子弾力性が無限大である。
ウ 投資需要の利子弾力性がゼロである。
エ 投資需要の利子弾力性が無限大である。
また、利子率弾力性がゼロなのか、無限大なのかだけでも、半分に削れますね。
このような問題は簡単に2択まで絞れますので、普段から意識してみてください。
組み合わせ問題は仲間外れを疑う
最後に、「組み合わせ問題は仲間外れを疑う」です。
例えば以下のような選択肢があったとしましょう。
ア a:イギリス b:中国 c:日本
イ a:イギリス b:日本 c:中国
ウ a:中国 b:イギリス c:日本
エ a:中国 b:日本 c:イギリス
オ a:日本 b:イギリス c:中国
ここで、aが日本の選択肢は選択肢オしかなく、同じようにbが中国なのは選択肢イだけ、cがイギリスなのは選択肢エだけです。
a,b,cのどれか1つだけ分かった瞬間に、正解が選べてしまうような問題は出題される可能性が低いので、これらの除外すると、選択肢イかウが正解である可能性が高いと判断できます。
実際、この問題の正解は選択肢イでした。
以上、確実に正解が選べるテクニックというわけではありませんが、迷ったときに使える内容と思います。
まずは過去問対策で十分な知識を身に付けた上で、テクニックも駆使して合格を掴み取ってください。
また宜しければ、ご自身なりの解答テクニックがありましたら、コメント欄でご共有いただければと思います。
まとめ
それでは最後にまとめです。
今回は、本試験では、自信を持って正解できる問題、確率で正解できる問題、全くわからない問題が出題され、それらの合計で60点以上を確保するという合格イメージをお伝えしました。

これは、全25問中、自信を持てない問題が半分以上あることを意味します。
ですので、本試験中は、どの科目でも60点を超えた感覚が持てず、かなり精神的に追い込まれるかと思います。
もちろん実際の難易度設定はもう少し緩く、自信を持って正解できる問題だけで60点を超える科目が出題される場合もありますが、このような理解をしておいた方が、本番は落ち着いて対応できるかと思います。
はい、というわけで、今回は一次試験の得点パターンとその対策をテーマに解説してみました。
今回解説した通り、本試験では得点すべき問題と、そうではない問題が散りばめられています。
作問者が取らなくてもよいと考えている問題まで攻略しようとすると、通常の倍以上の勉強量が各科目ごとに必要なりますので、かなり費用対効果が低いと思われます。
今回の内容を参考に、日々の勉強に取り組んでみてくださいね。