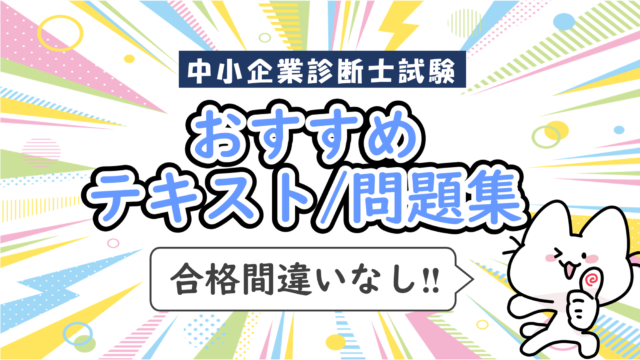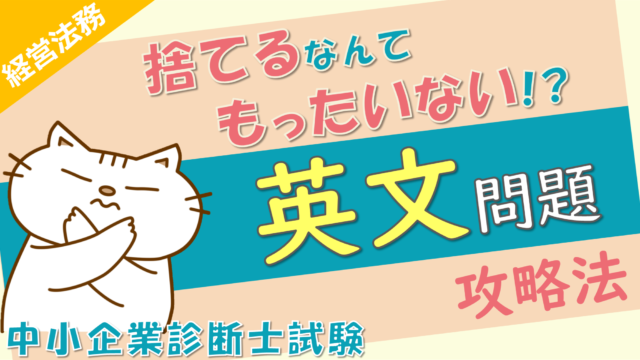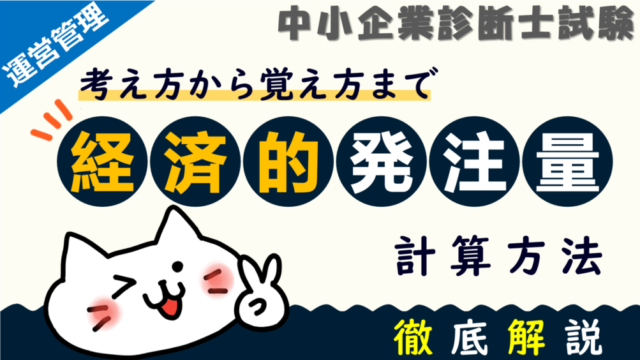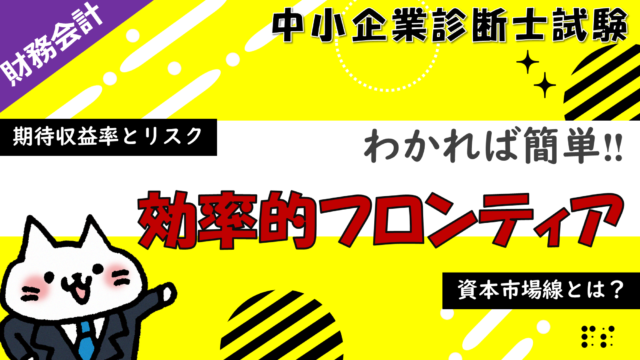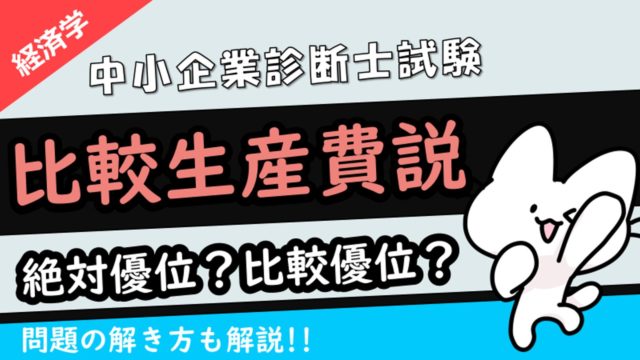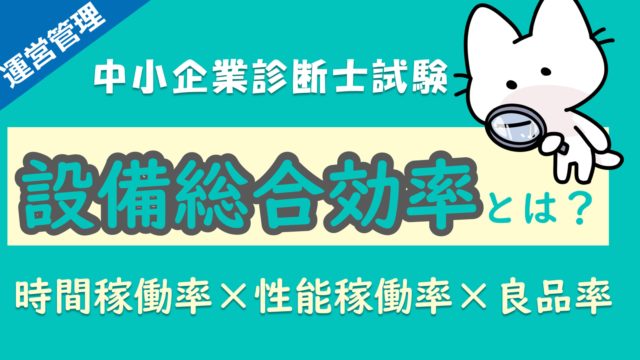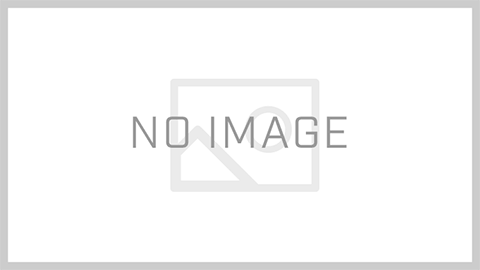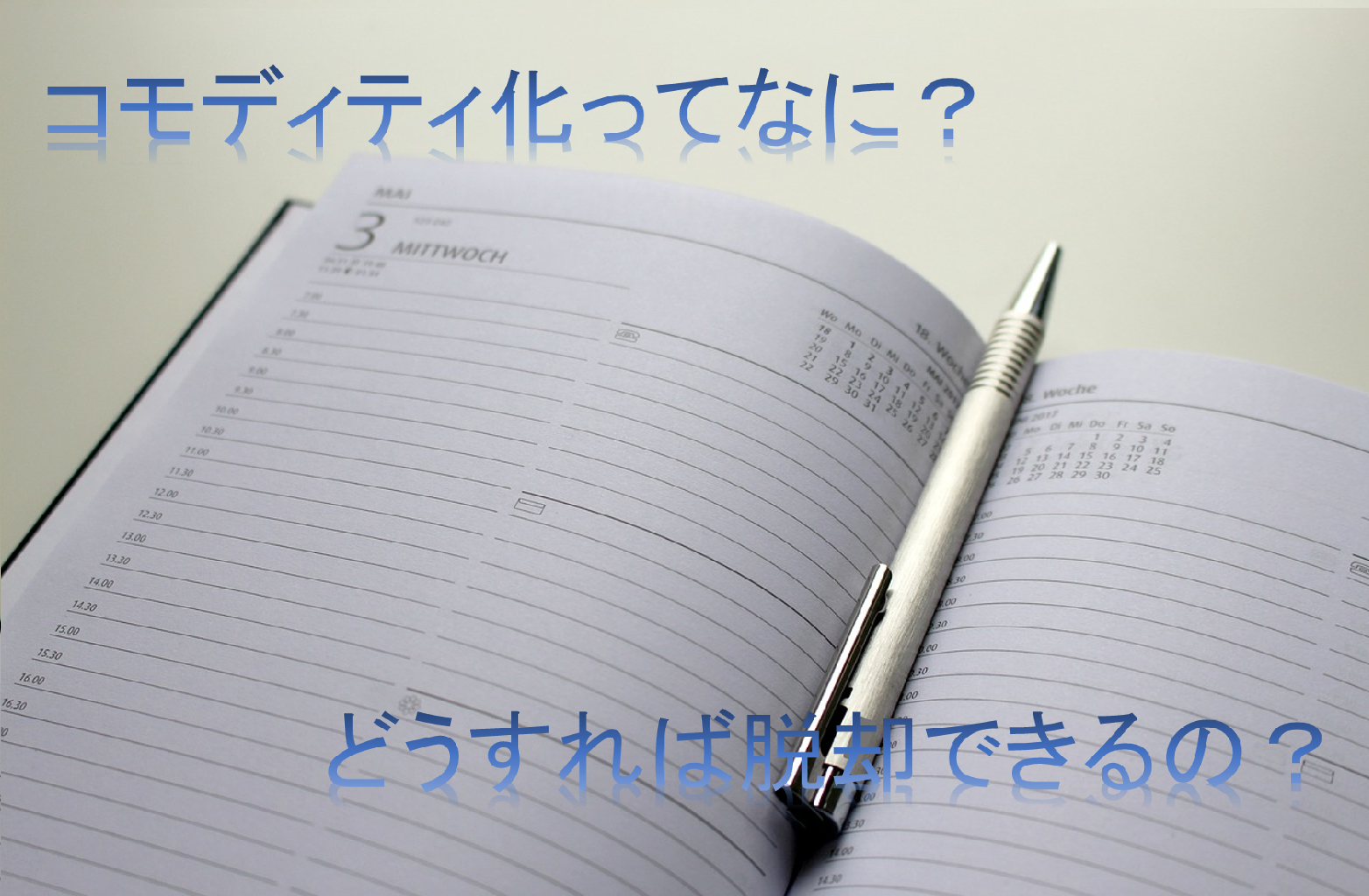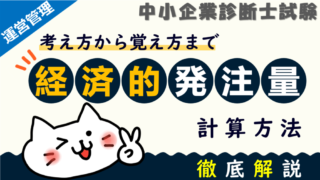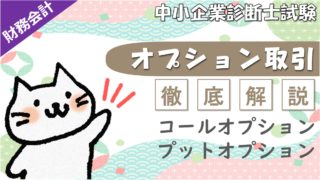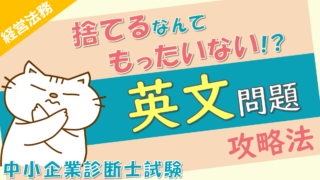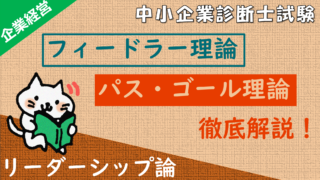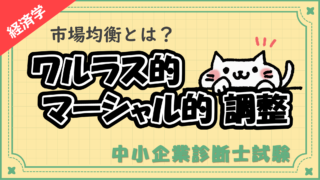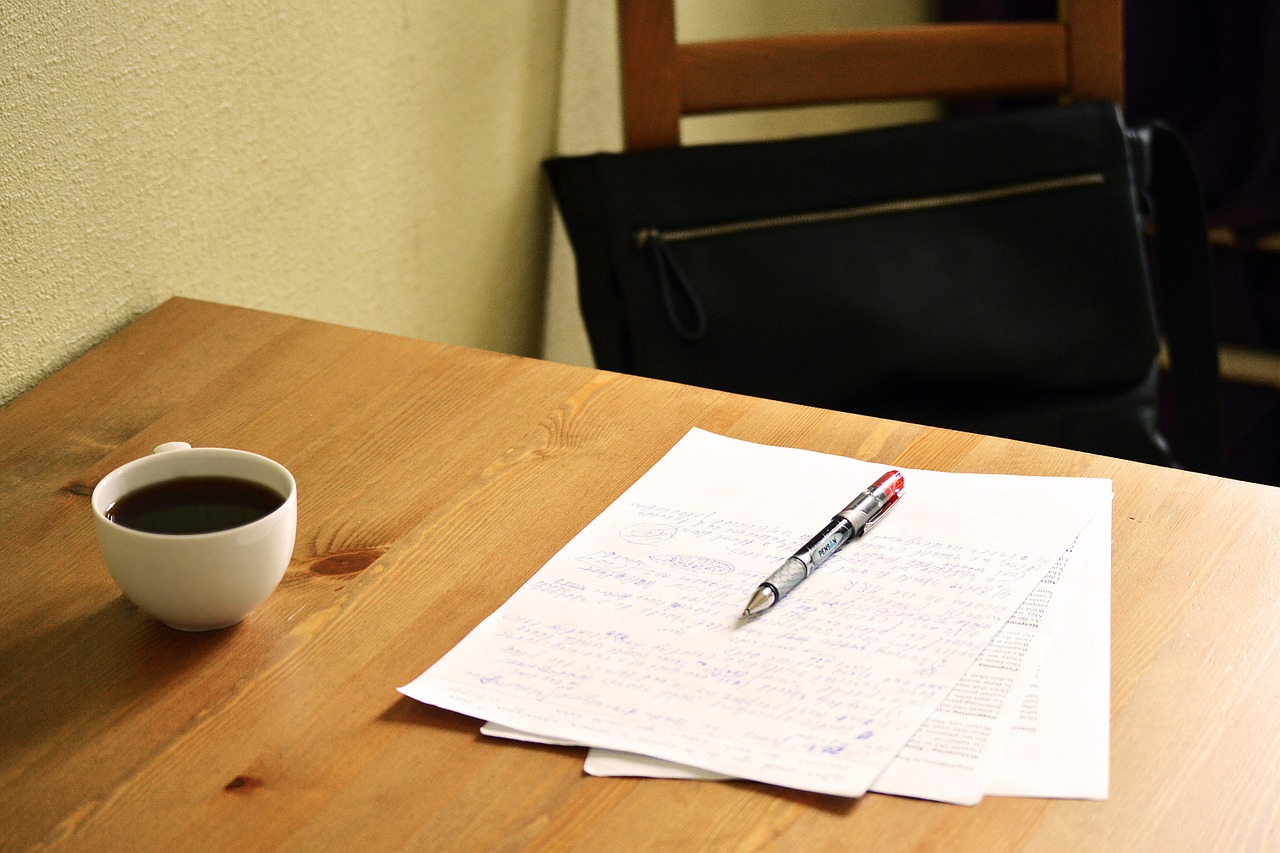-
 中小企業診断士
中小企業診断士試験におススメなテキスト・問題集をご紹介し...
中小企業診断士
中小企業診断士試験におススメなテキスト・問題集をご紹介し... -
 一次試験対策
【経営法務】捨てるなんてもったいない!?英文問題の攻略法...
一次試験対策
【経営法務】捨てるなんてもったいない!?英文問題の攻略法... -
 一次試験対策
【中小企業診断士】一次試験の勉強方法とは?
一次試験対策
【中小企業診断士】一次試験の勉強方法とは? -
 一次試験対策
経済的発注量(EOQ)の計算式の考え方・覚え方を徹底解説...
一次試験対策
経済的発注量(EOQ)の計算式の考え方・覚え方を徹底解説... -
 一次試験対策
【ファイナンス】効率的フロンティアと資本市場線の考え方を...
一次試験対策
【ファイナンス】効率的フロンティアと資本市場線の考え方を... -
 一次試験対策
【企業価値】MM理論の考え方・計算式をわかりやすく解説し...
一次試験対策
【企業価値】MM理論の考え方・計算式をわかりやすく解説し... -
 一次試験対策
比較生産費説とは?絶対優位と比較優位の違いと問題の解き方...
一次試験対策
比較生産費説とは?絶対優位と比較優位の違いと問題の解き方... -
 一次試験対策
設備総合率の計算方法を解説!時間稼働率・性能稼働率・良品...
一次試験対策
設備総合率の計算方法を解説!時間稼働率・性能稼働率・良品...
おすすめ記事
最新記事
-

【為替】外国為替レートの4つの決定要因を解説!アセットアプローチ・フローアプローチ・購買力平価説・金利平価説とは?/経済学/中小企業診断士試験対策
-

【デジタルマーケティング】トリプルメディア~ペイドメディア・オウンドメディア・アーンドメディア~を解説します!/企業経営理論/中小企業診断士試験対策
-

【まちづくり三法】大規模小売店舗立地法・中心市街地活性化法・都市計画法の違いを解説します!/運営管理/中小企業診断士試験対策
-

【中小企業診断士試験】たかぴーのおすすめオリジナル教材たちをご紹介します!!
-

【効率的市場】ウィーク型・セミストロング型・ストロング型仮説の違いとは?/財務・会計/中小企業診断士試験対策
人気記事
サイト内検索